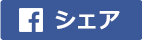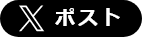コンプライアンスの推進や危機管理体制の再構築に向けた取組み
危機管理体制を見直しました(平成24年7月)
- 東日本大震災や意見投稿要請問題への対応状況等を踏まえ、様々な危機に迅速・的確に対応するため、副社長を委員長とする「危機管理体制あり方検討委員会」を設置し、危機管理体制の見直しについて検討を行いました。
- 委員会においては、
-
- 対応すべき危機を明確にし、事前の予防や発生時の対応準備に全社が一体となって取り組む仕組み
- 危機発生時には、迅速な経営判断と全社の機能・能力を結集して適切な対応を可能とする体制の整備について検討を進めてきました。
- 主な見直し内容は以下のとおりです。
-
- 危機管理官(危機管理担当副社長)及び危機管理担当部長を設置するとともに、各本部に危機管理担当(兼務者)を設置するなど体制を強化
- 「リスク・危機管理対策会議」を設置し、リスク管理と危機管理の連携及びマネジメントサイクルの推進機能を強化するとともに、危機発生時の情報共有や対応能力を強化
- 専門的・先進的な知見を有する社外専門家(シンクタンク)による総合的な支援体制を整備
コンプライアンス推進体制を見直しました(平成24年5月~7月)
意見投稿呼びかけ問題等の原因分析に基づく信頼再構築に向けた取組みとして、コンプライアンス委員会及びコンプライアンス推進体制に関する以下の強化施策を実施しました。
(1)コンプライアンス委員会の機能強化
社会的影響の大きい不祥事等発生時には、社外委員から助言等を受けるなど、委員会機能を強化
- 委員会事務局は、当該不祥事等について、速やかに社外委員へ情報提供
- 社外委員から助言等を受けた場合は、同事務局は遅延なく関係箇所へ報告
実施時期:平成24年5月
(2)コンプライアンス所管部門の一元化
責任体制を明確化し、主体的に全社のコンプライアンス経営を推進するため、コンプライアンス所管部門を一元化
- 地域共生本部、人材活性化本部、経営管理本部で分担しているコンプライアンス推進業務(注1)をすべて地域共生本部に一元化(注2)
(注1)業務計画・実績管理、相談窓口、教育、委員会事務局
実施時期:平成24年7月
(3)全支社へのコンプライアンス担当職位の設置
従業員のコンプライアンス意識の継続的な醸成(教育・研修)、不祥事等の兆候把握機能の強化(問合せ窓口の設置)等を目的に、「コンプライアンス支社所管エリア担当」を設置
- 東京支社を除く各支社所管エリアに支社長直結の「コンプライアンス支社所管エリア担当」(課長クラス1名)を設置
実施時期:平成24年7月
(注2)コンプライアンス所管部門の一元化
| 従来 | 平成24年7月以降 | ||
|---|---|---|---|
| 地域共生本部 |
|
地域共生本部 |
|
| 人材活性化本部 |
|
||
| 経営管理本部 |
|
||
社外役員と経営トップとの意見交換を実施しました(平成24年4月18日)
当社では、経営環境の変化に伴う様々なリスクや対処すべき課題等について、広く意見交換を行い、相互認識を深めることなどを目的に、4名の社外役員(取締役1名、監査役3名)と貫正義(代表取締役会長)、瓜生道明(代表取締役社長)による意見交換会を実施しました。
コンプライアンス講演会(大分支社)を開催しました(平成24年3月22日)

当社は、経済産業省主催の県民説明番組への意見投稿呼びかけ等の一連の事象に関して、再発させないために、社員の経営環境の変化への対応力向上を目的に、平成24年3月22日、大分支社(大分県大分市)にて、大分エリアの社員約140名を対象に、コンプライアンス講演会を開催しました。
講師には、企業における、組織の体質改善などのコンサル経験が豊富な専門家をお招きし、「経営環境の変化に柔軟に対応できる組織風土とは」というテーマで、電力業界での環境変化や、企業不祥事発生後における、現場から出来る組織風土の改善・改革事例などについてお話しいただきました。
講演会のまとめには、事業現場間の対話や社外の意見の取り入れにより、課題の把握・解決策立案へつなげること、それを実現するためには、社員の意識と行動が重要であるとのご提言をいただきました。
今後、大分エリアでは、今回の講演会で得たことを参考に、階層別に、意見交換を行う場を設け、組織風土改善に向けた具体的な施策の検討をおこなってまいります。
コンプライアンス講演会を開催しました(平成24年2月10日)

当社では、2月10日に福岡市内の本店にて、当社及び当社グループ会社の経営幹部約180名を対象に、コンプライアンス講演会を開催しました。
講師に、企業での実務経験を持つ大学教授をお招きし、「企業不祥事の発生と経営幹部の役割について」というテーマで、近年の企業不祥事の特徴や背景を踏まえた、企業のコンプライアンスのあり方や経営幹部の役割についてお話いただきました。
当社は、今回の講演を経営幹部のコンプライアンス意識向上につなげるとともに、今後の信頼回復に向けた施策に活かしてまいります。
講演の概要や資料は、社内で情報共有を行い、各職場における教育や研修に活用します。
eラーニングによるコンプライアンス研修
全社員を対象にコンプライアンス教育を実施しました
(平成24年1月~3月)

JMAMeラー二ングライブラリ
「最新事例に学ぶ 企業倫理・コンプライアンス実践コース」より
【制作·著作】
株式会社日本能率協会マネジメントセンター
Copyright 2011 JMA Management Center Inc.
平成24年1月から3月にかけて、全社員を対象としたeラーニングによるコンプライアンス研修を実施しました。
意見投稿要請問題等の事案を織込み、社会から求められるコンプライアンスについて理解を深めるとともに、業務遂行にあたっての判断基準を習得し、実践に繋げることを目的として実施しています。
また、eラーニングによる研修受講後には、自職場におけるコンプライアンスについて職場で話し合う、職場内学習も実施しています。
なお、上記に加えて原子力部門等に対しては、平成23年11月から平成24年1月にかけて、社外講師によるコンプライアンスセンス(感性)やマネジメントのあり方等を習得するためのコンプライアンス教育を実施しました。