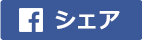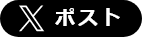安全性
原子力に関するよくあるご質問
原子力発電所の地震対策はどうなのですか。
原子力発電所の耐震設計は、原子炉容器、原子炉建屋、制御棒駆動装置、原子炉格納容器、使用済燃料プールなどの重要な建屋・機器については原子炉を安全に「停止し」「冷やし」、放射性物質を「閉じ込める」機能が十分保てるように、厳しい耐震設計(注)を行い、設計されています。
(注)基準地震動Ssに対して、設備が耐えられるかどうか、コンピュータの解析により確認します。
当社原子力発電所の基準地震動Ssとは、安全上重要な建屋・機器の耐震設計に用いる基準となる地震動で、新規制基準に基づき、以下の内容を考慮して策定されます。
- 敷地ごとに震源を特定して策定する地震動:発電所周辺にある活断層などから考えられる最大の地震動
- 震源を特定せず策定する地震動:震源と活断層の関連付けが難しい過去の地震に基づく地震動
(例:平成16年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動、標準応答スペクトルを考慮した地震動)
また、原子力発電所の地震観測データについては、以下「玄海(川内)原子力発電所の地震観測データ」をご参照ください。
原子力発電所の高経年化の安全規制と運転期間に関する新しい制度とはどのようなものですか。
2023年5月のGX脱炭素電源法の成立に伴い、電気事業法や原子炉等規制法が改正(2023年6月公布、2025年6月施行)され、高経年化した原子力発電所の安全規制と運転期間に関する制度が見直されました。
新しい制度では、運転開始から30年を超えて運転する場合、原子炉等規制法に基づき、10年を超えない期間ごとに長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが必要になり、安全規制が強化されました。
また、原子力発電所の運転期間に関する法律が、原子炉等規制法から電気事業法に変更となり、運転期間については、これまでと同様原則40年とされ、原子力規制委員会による安全性の確認を大前提に、安定供給の確保やGXへの貢献、自主的安全性の向上や防災対策の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に限り延長が認められます。
なお、延長期間は、これまでと同様20年を基礎として、原子力事業者が予見しがたい事由(安全規制に係る制度・運用の変更など)による停止期間を考慮した期間に限定されます。
原子力発電所で働いている社員の教育や訓練はどのようなものですか。
原子力発電所の運転員は、まずは発電所内の巡視員からはじまり、タービン・電気運転員、原子炉運転員などの経験を積み重ね、約10年かけて一人前の運転員になります。また、技術レベルの維持・向上を図るため、定期的に教育・訓練を社内・社外でおこなっています。
また、運転員の責任者である当直課長は、国が定める基準に合格しており、定期的に第三者機関による厳しい試験や訓練で、知識・技能が維持されていることが確認されています。
なお、発電所構内には、発電所の運転を行う中央制御室をそのまま模擬した運転シミュレータや、機器や電気設備などの訓練設備を備えた「原子力訓練センター」があり、運転員は運転シミュレータを使って事故時の対応などの運転訓練を行い、また、保修員は機器の点検・組立や動作試験などの訓練を行うことによって、技術向上を図っています。
原子力発電所からは放射性物質がでているのではないですか。
原子力発電所の運転により、周囲の人が受ける放射線の量は極めて低く、年間0.05ミリシーベルトの線量目標値に対し、実際はその50分の1の0.001ミリシーベルト未満です。
一方で、宇宙や大地など自然界に存在する放射線を自然放射線といい、人間1人あたり年間平均2.4ミリシーベルト(世界平均)の自然放射線を受けています。
したがって、原子力発電所の運転により、周囲の人が受ける放射線の量は、自然放射線の1000分の1未満となります。
当社と自治体が行う環境放射線モニタリングにおいて、発電所周辺の海水や土などの放射性物質の濃度を定期的に測定し、その調査結果については、学識経験者も参加する自治体主催の会議において、環境への影響がないことが確認されています。
原子力発電所ではどのような安全対策をしているのですか。
国は、福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、新規制基準を策定し、万一、想定外の事象により、従来から設置していた設備が使えない場合でも、原子力災害(重大事故)に至ることを防止したり、原子力災害に至った場合でも、その影響を緩和するために有効な複数の対策の整備を求めました。
当社は、新規制基準の深層防護の考え方に基づき、新たに特定重大事故等対処施設を設置するなど、設備面での幾重もの安全対策を実施するとともに、万一の重大事故発生時にも速やかに事故収束できるよう体制や手順を整備し、日々、様々な訓練を積み重ね、対応能力の維持・向上に取り組んでいます。
また、更なる安全性及び信頼性の向上のためには、規制の枠にとどまることなく、自主的かつ継続的に取組むことが重要であり、新規制基準適合後も最新の知見などを踏まえた安全性向上への取組みをおこなっています。
今後とも、福島第一原子力発電所事故に対する調査結果や技術的知見の収集に努めながら、新たな知見が得られれば、しっかりと検討を行い、反映してまいります。
原子力発電所の安全対策については、以下の各発電所パンフレットに記載していますので、ご参照ください。