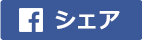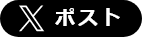薩摩川内市・丸武産業(2)
2015年1月29日
-甲冑に込められた武将たちの思い-
前回に続き、鹿児島県薩摩川内市で、兜や甲冑などを製作している丸武産業をご紹介します。

企画営業本部長の平林正勝さんに、時代の変遷とともに移り変わった甲冑のデザイン性などについてお話しを伺いました。
「かつて甲冑は、武士が戦場で身を守る防具であるとともに、戦場での死に装束としての神聖さも備えていたと考えられます。 平安から江戸へと時代を重ねるごとに、武具としての機能性はもちろん、自分を表現するためのデザイン性も加わり、甲冑は武士にとって自身の化身といっても過言ではない装束でした。

平安時代から戦国時代まで、刀から槍、弓矢、鉄砲へと戦術が変わると共に、甲冑の仕様も変わっていきました。 馬上で弓を射る騎射戦が主だった平安・鎌倉時代は、矢の攻撃に備え、大袖が立派なのが特長です。
鎧部分には皮や鉄製の板がつなぎ合わされており、糸紐をたくさん使って作られていました。

そして、安土・桃山など戦国時代になると鉄砲が戦場で使用されるようになり、『伝統的な鎧に比べて新しい』という意味を含んだ『当世具足(とうせいぐそく)』と呼ばれる甲冑が主流となりました。
鉄の加工技術が上がったことから、胴は強固で防御性に優れた一枚ものとなり、兜の装飾もより個性豊かなものとなっていったんです。

特に戦国時代は、広い戦場の中で自身の個性や強靭さ、脅威を与えるために、各武将がそれぞれ趣向を凝らしていて、興味深いですね。
どの甲冑を見ても、先人達の並々ならぬ思いが詰まった『魂』が、その細やかな造りとデザイン性から感じられます」
同社では、そんな先人たちの「魂」が表現された甲冑の素晴らしさを多くの方に伝えたいと、国内外で甲冑の展示会やイベントをおこなっています。さまざまなタイプの甲冑が一堂に会する展示会はいつも大盛況で、老若男女、多くの方が訪れるそうです。

「国内はもちろん、海外でも『甲冑に宿る武士の魂が素晴らしい!』と人気が高いです。さらに海外の甲冑と比べ、発想が柔軟で、デザイン性に長けたものは類い稀だと、海外デザイナーの関心も高いですね。
今後も海外に日本の伝統文化・甲冑の素晴らしさを伝えたいと思い、台湾での展示会を予定しています。いずれはドバイでの展示会もチャレンジしてみたいです!」

次回は、丸武産業のものづくりの現場をご紹介します。