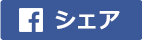1960年代のあゆみ
経営基盤の安定と体質強化
日本経済は設備投資の活発化や主要産業の業績好調により、高度成長を遂げていった。
九州電力は需要の順調な伸び、高効率大容量火力発電による経済性の向上、重油価格の低下などで経営収支は安定したが、低い労働生産性を改善するための合理化、経営体質の強化を全社一丸となって進めた。
時代背景
高度成長と国際化
この10年間は、民間の設備投資が活発化し、鉄鋼・化学・自動車などの主要産業が好調で、日本はいざなぎ景気を経て右肩上がりの経済成長を遂げていった。また、政府の所得倍増計画が進捗し、雇用の増大や所得の向上がもたらされ、日本は社会の安定と国民の自信を取り戻した。
一方、1964年には外国為替自由化の義務を負うIMF(国際通貨基金)8条の指定国になり、さらにOECD(経済協力開発機構)加盟を果たすなど国際化への道を歩み出した時代でもあった。
公害問題の浮上と公害防止協定の締結
1960年代後半に入ると四日市ぜんそくや水俣病などの公害問題が全国的に発生した。特に四日市ぜんそく訴訟では、大気汚染の責任に加え、気象条件など総合的な調査研究を怠ったとして、立地上の過失を指摘された。そのため、環境の保全・改善が国家的課題となり、企業も一層の公害防止対策を迫られるようになった。
地方自治体は逐次、公害防止条例を制定し、硫黄酸化物や窒素酸化物などの排出基準を強化した。
九州電力では1969年の苅田発電所をはじめとして、唐津・相浦・港発電所と順次、公害防止協定を締結していった。
需要の変化
電灯需要の増大と大口電力需要の伸び悩み
1970年度の販売電力量は188億kWhとなり、この10年間の年平均伸び率は7.7%であった。
この間の需要の特色の一つに電灯需要の増大があげられる。家庭電化機器の普及は急速に進み、1970年には白黒テレビ、冷蔵庫、洗濯機などの普及率は100%近くとなり、さらには生活水準の向上にともない、カラーテレビ、クーラーなどが普及し、第2次電化ブームを引き起こした。この10年間の電灯需要の年平均伸び率は13.9%にもなり、1960年度には15%であった電灯需要の構成比は、1970年度には26%へと著しく増加した。
一方、電力需要については、この10年間に業務用電力が年平均伸び率17.1%の高い伸びを示したものの、大口電力は4.5%と伸び悩んだ。この結果、電力計で年平均伸び率6.2%の伸びにとどまり、全国平均の11.1%を大幅に下回った。
産業別にみると、石炭が相次ぐ炭鉱閉山で1960年度に比べ半減、化学はアンモニアやソーダをはじめ製品全体の生産が前年の伸びを下回ったこと、自家発電量が増大したことなどから1.3倍と低い増加となった。鉄鋼も1969年7月の戸畑共同火力1号機の運転開始、自家発電設備の増強により、1.8倍の増加にとどまった。セメントは公共投資、民間設備投資の活況などにより3.7倍の増加となった。
冷房需要の増大による夏季ピークヘの移行
この10年間の最大電力は冷房需要の増大などにより約200万kW(年平均伸び率8.0%)の増加を示し、1970年度は約373万kWとなった。
年間最大電力は、1967年度までは冬季点灯時の19時から20時にかけて発生していた。しかし、家庭用ルームクーラーの普及や商業ビル、事務所などの空調・冷房設備の増加にともない、1968年度から夏季昼間帯の14時ごろに発生するようになり夏季ピーク型に移行した。
また、昼間需要の増加に対して深夜需要の伸びは小さく、昼夜間格差は拡大した。
電源の拡充
高効率大容量火力発電所の建設
この10年間、火力発電は技術的に著しい進歩を遂げた。九州電力は最新鋭の高効率大容量火力をベース電源として開発を進め、九州電力初の制御用電算機を採用した唐津発電所1号機などの15万6000kW級5基と、九州電力初の重油専焼ボイラーを採用した大分発電所1・2号機の25万kW級を建設した。
石炭から石油へのエネルギー転換
1955年代の後半から「石炭から石油へ」というエネルギー革命が進行したことで、九州電力は石油価格の急速な値下がりと輸送面・環境面での技術的優位性を重視し、石炭火力から重油火力への転換を図った。石炭火力は1967年9月運転開始の唐津発電所1号機を最後に建設を中止し、既設石炭火力の重油専焼化を苅田発電所1号機を皮切りに進めていった。
また、1969年7月には九州電力初の重油専焼大分発電所1号機の運転を開始した。
原子力開発への取り組み
九州電力は、原子力発電の準国産エネルギーとしての優位性に着目し、電源多様化の中核として原子力の開発を推進してきた。
1950年代後半に入り、総合研究所に原子力研究室を設置して体制を整えるとともに、社員を国内外の原子力関係施設に派遣し、要員の養成と実務経験者の確保を図った。そして、原子力発電導入の方針を決定するとともに、1969年7月には原子力建設部を設置し建設体制を確立した。
収支安定と合理化
経営収支の長期安定
この10年間は、高度経済成長で電力需要が年平均7%以上の高い伸びを示し、収入は1970年度には1485億円と1960年度の2.9倍になった。
一方、支出は収入の伸びをやや下回り2.8倍となり、経常収支が安定した時期であった。これは人件費などが3~4倍に伸びたものの、燃料費が石炭価格の引き下げなどで1.8倍、資本費が低金利政策などにより2.7倍と低い伸びに留まったためである。
また、電気料金についても1961年以降は需要の順調な伸びに加え、高効率大容量火力発電による経済性の向上、重油価格の低下などの要因によって、1974年6月の改定まで維持することができた。
経営の合理化
九州電力は、営業エリアに離島が多いことによるコスト高や労働生産性の低さなどの経営課題を抱えていた。そのため、1955年に合理化委員会、1959年に常務会を設置し、これらの組織体制のもとで各種の合理化を推進した。
さらに、1968年1月には社達「経営能率の刷新について」を示達し、現業事業所の統廃合やスタッフ部門の組織変更ならびに委託化・請負化などの合理化を推進した。
サービスの向上
停電の減少と未点灯家屋の解消
お客さまに停電の少ない良質な電気を供給するために、電源・輸送設備の拡充・改良などの対策を鋭意推進してきた結果、この10年間で、設備の事故件数は10年前の約43%に減少したほか、お客さま1戸当たりの停電回数、停電時間は、それぞれ25%、44%に減少した。
また、九州電力は公益事業の責務として、未点灯家屋の解消に積極的に取り組んだ。その結果、創立当時5万5000戸余りあった未点灯家屋が1970年度末には全面的に解消した。
地域社会への協力と連携
電力供給が安定した1950年代後半は、活発なサービス活動を実施した。1960年以降、各支店にサービスセンターを設置して婦人電気教室を開催するなど、活動の重点をサービスの改善や電力の使用促進を目的とするものへと移していった。
1960年代後半に入ると、電気への依存度は高まり、電気事業に対する社会的要請も高度化・多様化してきたため、1966年度からは各営業所で消費者団体など各界の代表者を対象にサービス懇談会を開催し、九州電力への意見や要望を聞くとともに九州電力の実情を説明するなど、地域のお客さまとの対話を基調としたサービス活動を展開した。